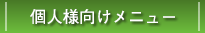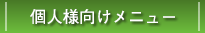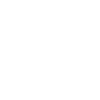
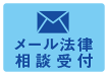

|
■離婚事件の手続き
離婚を行う場合,次のような手続きを行う必要があります。
| | (1) |
協議離婚
当事者が協議の上,離婚届を役所に提出します(離婚届では親権の帰属者を記載する必要があります)。
|
| |
| | (2) |
調停離婚
協議しても結論に至らない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では,2人の調停委員に双方から話をし,調停委員が調停の成立を試みます。
調停は,あくまで話し合いなので,当事者双方が合意した場合に限り,調停成立となります。
|
| |
| | (3) |
裁判離婚
調停が成立しない場合,家庭裁判所に離婚を求める訴えを提起することになります。
なお,裁判離婚の前に必ず離婚調停の手続を践む必要があります。
裁判では,離婚の原因が法定されているので(民法770条1項1号〜5号),そのような法に定められた離婚原因が存在するのか否かが争われることになります。
(離婚原因)
1. 配偶者に不貞な行為があったこと
2. 配偶者から悪意で遺棄されたこと
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないこと
5. その他,婚姻を継続しがたい重大な事由があること
(たとえば,暴力,浪費,性の不一致,性格の不一致,宗教の不一致など)
|
■離婚事件の争点
離婚事件では,
(1)離婚そのもの
(2)親権の帰属(これに付随して,養育費,面接交渉なども争いになる)
(3)慰謝料の有無,金額
(4)財産分与の方法
が争いになります。
| | (1) |
離婚そのもの
上記の離婚原因の存否が問題になります。 |
| |
| | (2) |
親権の帰属
まず,どちらを親権者にするかが問題で,実際の裁判などでも,最も争いになる部分です。
親権者を決める基準は過去の裁判例を参考にすると,監護体制の優劣,子に対する愛情,心身の健全性,子の年齢,養育環境の継続性,子の意思などを総合的に考慮して決定されています。
また,親権者となった親から,他方の親に対して,養育費を請求することもできます。
養育費の金額については,養育費算定表というものがあり,概ねこの算定表に従って金額が算出されます。さらに,親権者となるのは難しい場合であっても,子供に一定の頻度で面会することを求めることもできるのが一般的です。 |
| |
| | (3) |
慰謝料の有無,金額
慰謝料の発生を認めることができるような事情(不貞行為,暴力など)があるか,それを証明する証拠(写真,手紙,診断書,目撃者など)があるかが重要です。
金額的には,裁判所が裁量で決定することが多く,一般的には,夫の不貞行為が原因の場合,200〜300万円程度であるとされております。 |
| |
| | (4) |
財産分与の方法
夫婦の共有財産(結婚後,2人が協力して得た財産)があるか,あるとしてどのように分けるかが問題になります。なお,夫婦の一方が,親から相続した財産などは特有財産といい,財産分与の対象とはなりません。
分与の割合は,最近は,2分の1ずつが多いようですが(2分の1ルールと言われることもあります),争いになることもあります。
分与の方法で最も難しいのが,住宅があって,住宅ローンが残っている場合です。住宅を売るのか,どちらかが住み続けるのか,住宅ローンを誰が負担するのかが問題になります。
なお,従来問題のあった年金については,現在では年金分割制度が立法化され,年金の分割もできるようになっています。
|
■弁護士が関与することによるメリット
| | (1) |
交渉の煩わしさを回避できる
離婚後の生活のことを考える必要があるのに,離婚の原因がどこにあるのか,財産をどのように分割するのかなどについて,夫ないし妻と交渉しなければならないのは煩わしいものでしょう。
弁護士は,過去の裁判例や自分の経験をもとにして,どのように交渉するのが最も依頼者の利益になるのかを考えながら,交渉を重ねていきますので,面倒で,効果のない交渉を自分で行うことを回避できます。 |
| |
| | (2) |
戦略的に考えることができる
弁護士は,交渉によって協議離婚で解決するのがよいのか,調停を申し立てた方がよいのか,裁判にした方がよいのか,相手方の財産をあらかじめ仮差押えしておいた方がよいのかなどを,依頼者とともに戦略的に検討しながら,事件を進めていきます。交渉のみによって適切な解決ができる場合には協議離婚を行って解決しますので,弁護士であるからといって,必ず裁判にするというわけではありません。私の経験でも,協議離婚で解決する事件も相当数あります。
裁判まで視野に入れて事件を進めることができるのは,行政書士など弁護士以外の者にはできないことでしょう(なお,行政書士は訴訟はもちろん,交渉事件の代理人となることもできません)。
弁護士に依頼するのは,裁判になってからでよいという意見もあるようですが,裁判でも,それまでの交渉経過がものをいう場合がありますし,交渉段階から裁判もありうるということを念頭に置いて戦略を立てて交渉に臨むことが事件解決にとって有意義であることはいうまでもありません。
離婚事件は,一生に一度経験するか否かというような重大な事件なのですから,弁護士に依頼して,総合的な解決を図るのが望ましいと思います。
|
■弁護士費用について
着手金
(算出一例) |
●交渉事件(裁判外)・・・21万円
●調停事件(裁 判)・・・21万円
↓事件移行の場合,差額金として10万5000円を申し受けます
●訴訟事件(裁 判)・・・31万5000円 |
| 最終報酬 |
基準額の31万5000円に財産分与,慰謝料などの財産給付を伴う場合,下記の「弁護士報酬規定経済的利益算出表」に当てはめ算出し,その額を基準額31万5000円に加算する。 |
| (算出一例) |
離婚が成立し,かつ財産分与,慰謝料などの財産給付の合計が500万円と認められた場合,算出表のとおり,経済的利益の15%+消費税となるので,110万2500円が最終報酬となります。
つまり,離婚のみが成立し,他に受け取る財産給付がなければ,最終報酬は31万5000円になります。 |
■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。
| 交渉 |
電子内容証明郵便を相手方へ発送
↓
発送後,2週間程度相手方の応答を待つ
↓
相手方が交渉による話し合いに応じない場合,調停または訴訟へ移行する
申立書を裁判所へ提出
↓(適宜 打合せ)
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
調停終了(和解成立)または不調(調停不成立)の場合訴訟へ移行
↓(適宜 打合せ)
訴状を裁判所へ提出 (第1審)
↓(適宜 打合せ)
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
↓(適宜 打合せ)
判決内容に不服がある場合控訴する
(※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意) |
| 調停 |
| 訴訟 |
■弁護士報酬規定経済的利益報酬算出表
| 経済的利益
| 着手金
| 報酬金 |
|---|
| 300万円以下の場合 |
21万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 300万円を超え500万円まで |
31万5,000円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 500万円を超え1,000万円まで |
42万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 1,000万円を超え1,500万円まで |
52万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 1,500万円を超え2,000万円まで |
63万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 2,000万円を超え2,500万円まで |
73万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 2,500万円を超え3,000万円まで |
84万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 3,000万円を超え3,500万円まで |
94万5,000円 |
300万円+3,000万円を超える部分の6%
+消費税 |
| 3,500万円を超え4,000万円まで |
105万円 |
330万円+3,500万円を超える部分の5%
+消費税 |
| 4,000万円を超え3億円まで |
3%+消費税 |
355万円+4,000万円を超える部分の4%
+消費税 |
| 3億円を超える場合 |
3%+消費税 |
1,395万円+3億円を超える部分の3%
+消費税 |
|