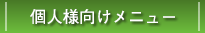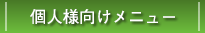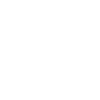
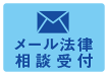

|
■処理方針
利息制限法に基づく引き直し計算を行ったものの多くの借金が残ったが,破産手続きは行いたくない場合に,法律に定められた範囲内でさらに借金の減額を行うことができる制度です。
会社の場合には,破産してしまうと営業活動をできなくなってしまうので,事業の再建を図り営業活動を継続したい場合に利用されます。会社の再建の場合,債権者と折衝を行うだけでなく,会計上の専門的な知識が必要になりますので,当事務所では,公認会計士と協力して事務処理を進めています。
また,個人の場合には,破産してしまうと仕事上の資格を失ってしまう場合(保険の外交員,警備員など),住宅を手放したくない場合(住宅ローン以外の借金を減額することによって,住宅ローンの支払いを楽にするという方法があります)に,民事再生手続きを選択するメリットがあります。
■弁護士費用について
再生事件の着手金は,資産や負債の額,債権者の種類,関係人の数
(※)事件の規模や事件処理に応じて各事案が異なるため,基準額に幅がある。
(※)同時に複数人が再生申立をする場合,
最初の一人が42万円二人目から31万5000円ずつ加算する。
(※)算出一例 家族3名が個人再生申立をする場合,合計105万円となる。
着手金
(算出一例) |
個人の場合・・・42万〜52万5000円
法人の場合・・・105万円〜210万円
|
| 最終報酬 |
なし(着手金に含む)
|
■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。
| 過払金がない場合 |
受任通知を債権者へ発送
↓※受任通知により,督促・返済中止の効力が生じる。
発送後,1ヶ月程度債権者より「債権届出書」到着を待つ
↓※1ヶ月経過しても届かない場合,督促する。
「債権届出書」到着後,法定利息への引き直し計算を行う。
↓
依頼者と再生申立の内容について打合せを行う
↓※補足的に電話,メールにて事情を伺う
「再生申立書」を作成
↓※補足的に電話,メールにて事情を伺う
地方裁判所へ「再生申立書」を提出
↓
裁判所より個人再生委員(弁護士・司法書士)を選任
↓※再生委員より手続開始に関する意見書が裁判所へ地方裁判所
より再生手続開始決定が発令
↓
再生委員の指定する預金口座へ再生申立人(依頼者)が毎月試験的積立を行う。この積立金は再生委員の報酬となる。
※積立額は毎月3万円が目安
※積立期間は4〜5ヶ月が目安
これは、再生計画に基づき毎月弁済できるかを試される期間であり、遅延すると認可されない場合もある。
↓
「再生計画案」を裁判所へ提出
↓※提出後、再生委員より2回の意見書が提出される
再生計画の認可・不認可の決定
↓
再生計画の認可確定
↓
認可確定の1ヶ月後から計画案に基づいて弁済開始
↓
事件終了となり,精算手続(実費算出)を行う
過払金を確認後,債権者へ「請求書」を発送
↓
依頼者へ「事件進捗報告書」により過払金額を知らせ,債権者との過払請求交渉を開始したことを報告する。
↓
債権者との交渉
交渉後,3ヶ月〜6ヶ月間で和解が見込めないと判断した場合,訴訟へ移行
|
過払金がある場合 |
| |
和解が成立した場合,「最終報告書」を発送し,精算手続(最終報酬
及び実費請求,相殺後返金)
|
| |
裁判所へ「訴状」を提出
↓
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
↓(適宜 打合せ)
事件精算手続(最終報酬及び実費請求,相殺後返金)
↓
判決内容に不服がある場合控訴する(※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意)
これ以降は 過払金がない場合 の進捗と同様
|
|